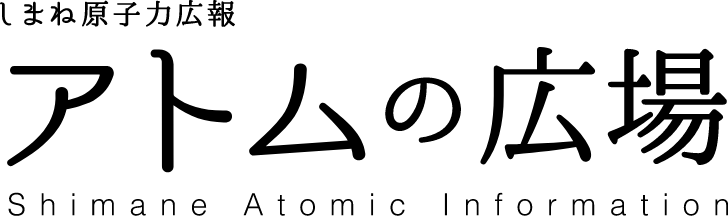この美味しいには、
理由がある!

島根に初夏の訪れを告げるトビウオを
ていねいにすり身にしてじっくり焼き上げる
これがなんとも旨い!
5月下旬頃から7月中旬にかけて山陰沖にやってくる島根県の魚「トビウオ」。こちらでは「あご」と呼ばれ、古くから親しまれてきた魚です。この時期のトビウオは産卵を終えたばかりで淡泊ながら脂がのっており、刺身や焼物としても美味しいですが、やはりお馴染みなのは「あご野焼き」。ふだんの食卓の一品として並ぶのはもちろん、ふいの来客の際のお茶請けや酒のあてとしても重宝する品です。氷もない時代に漁師が獲れたてのトビウオをすり身にして竹に巻きつけて野外で焼き、保存食としたのが始まりとされ、野焼きという名もこれが由縁で、その昔は松江のお殿様も食したという地域伝統食品のひとつです。
「かつては初夏になると、どの蒲鉾(かまぼこ)屋も店の軒先に焼き台を出してあご野焼きを作ったものです。あごの焼ける香ばしい匂いが辺りに漂って、松江の風物詩ともいわれていましたが、今ではすっかりなくなってしまいました」と言うのは松江市内で300年近く続く蒲鉾店の暖簾を守る青山昭さん。話のとおり現在では機械による生産が主流となり、昔ながらの手作業でのやり方は時代に合わなくなっているのも事実。それでも青山さんは昔ながらの製法にこだわります。「やっていることは昔とまったく同じで、原材料と製法をひたすら守っていくことが肝心だと思っています。島根県東部沿岸で初夏に水揚げされるトビウオだけを使い、地伝酒(じでんしゅ)で殺菌調味し、炭火で焼き上げる製法は変えることができません」と言います。その話からは松江が育んだ食文化を後世に残さなければという思いが伝わってきます。

すり身をアルミ棒に巻き付けながら手早く成形します。手作業ながらどれも同じ量、同じ形に。熟練の技が光ります。

トビウオを捌くときに出る頭や骨、皮などは肥料などに加工されます。「それもずっと昔からやっていたこと」と青山さんは言います。
地域の伝統食を後世に。
本物を正しくつくる、それだけです。
「あご野焼き」をつくる工程を拝見すると、大変に手間がかかっていることに驚かされます。まずトビウオを捌いて水でさらし、布袋で絞ります。この絞りの具合が大事で気温や湿度によって調整するといいますが、こればかりは長年の経験と勘によるところ。絞った魚肉はさらにミンチとカッターにかけて小骨やうろこを取り除き、石臼に入れて練ります。この練りの工程で地伝酒、粕取焼酎、塩などで味付けをします。この加減も老舗ならでは、まさに塩梅という言葉がぴったりです。そうして出来上がったすり身を1メートル以上もあるアルミ棒に手早く、器用に巻き付けていきます。形が整えられたすり身を炭火の焼き台の上でくるくると回しながら約30分かけてじっくりと焼き上げますが、その際に熱で皮が膨れて破れないように「突き立て棒」という剣山の針のような独特の道具でほとんど休むことなく叩き続けます。近くで見ていてもかなり大変な作業で、とくに夏場は「気温の暑さと炭火の熱さとでやっていられないほど」と焼き担当である青山さんの奥さんは笑います。

江戸時代中期の享保12年(1727年)創業という老舗を守る青山昭さんは14代目。現在は15代目の泰崇さんがその技を継いでいます。
出来上がった「あご野焼き」は外はパリッとしていて中身はやわらかく、噛みしめるごとに味わい深い旨みが口の中に広がっていきます。
「この時期のトビウオの美味しさは地元の人はよく知っています。ほど良い脂分と旨みがあって、やはりこちらで水揚げされるものは特別なんです」と青山さん。それに加えてトビウオは青魚が持つDHAやEPAの値も高く、健康促進や脳の働きにも効果があるといわれていますので食品の原材料としては一級品といえるかもしれません。この地元ならではの食材トビウオを、松江城下にしかない地伝酒で調味した、いわば松江だからこそできた郷土食。その飾り気のない朴訥な姿かたちの奥に、昔から伝えられてきた知恵と工夫が詰まっていました。

化学調味料や保存料は不使用。旬のトビウオのおいしさをていねいに練ることによって引き出します。
(※)「あご野焼き」には外国産の原材料を使用している製造業者・製品もあります。
■取材協力/有限会社青山商店